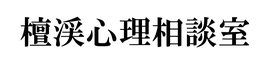今週は台風の到来で予定していたバーベキューが取りやめになって暇ができた。そこで私は初めてレンタルビデオの店に行って、映画を借りて来て見た。退職して、さらに台風の到来でやっとできたことで、私の新しい生活の一面が開けた思いである。映画監督は命を懸けて映画を作っているから、テレビドラマなどよりも遥かにインパクトが強い。映画が面白かったのでここに少し感想を書いておきたい。
映画は、監督がパトリス・ルコント。題名は『列車に乗った男』である。男が列車で町にやって、薬局に立ち寄った。狭心症の薬はなく、アスピリンを求めて出る。そこで出会ったもう一人の男はアスピリンを買った男に話しかける。その男は無口だが、これは発泡性の薬だという。それを飲むには水が要るねと、町の男は自分の家に誘う。男は彼の家に入って薬を飲んですぐに出て行こうとする。招いた男は、おしゃべりでいつも誰かとしゃべりたいから引きとめようとするけれど、男は宿を求めて出て行く。しかし、ホテルは休業で閉まっている。仕方なく男は彼の家に戻る。そこで最上等の部屋を提供される。そこから無口な男とおしゃべりな男のつき合いが始まる。
家の男は町にやって来た男の風来坊の生活にあこがれる。町にやって来た無口の男は、本当は仲間と銀行強盗をするためにやってきたのだが、元教師で、学校で詩を教えていたおしゃべり男の生活に次第に目を開いて、だんだんしゃべるようになる。一時は銀行強盗をやめる決心をするが、相棒の到着でやはり仲間との約束を果たすために銀行強盗を決行することになる。一方、家の男は病気になっていて手術を受けることになる。フランスではそうなのか、彼は手術の当日に病院に行く。彼も銀行強盗のために出かける。手術の時刻と銀行強盗の時刻が同じである。強盗は成功したが仲間の裏切りで彼は撃たれ、ほとんど即死のような重症を負う。手術を受けた男も医師のミスで心臓が止まって医師たちは治療を一旦あきらめてしまう。しかし、二人とも奇跡的に命が甦り、強盗した男は刑を受けて出所する。迎えに来た家の男は家の鍵を彼に与え、列車に乗って旅に出る。強盗をした男は家の主に代わって詩を教えるようになる。つまり、風来坊で無口な性格の男の人格と、おしゃべりで詩が好きで、じっと堅実に生きて生きた男の人格とが入れ替わるのである。
この人格の交代劇に、ほとんど死ぬような経験が織り込まれているのが興味を引いた。パトリス・ルコント監督も人格の変化のときに死に近い経験を用意したところが面白いと思った。私たちは心理臨床において人格変化や行動の改善を考えているけれども、人格、つまり、行動パターンや心構えの変化に死に近いような苦しみの過程が必要なことを忘れがちである。この映画は、そのことをもう一度思い起こさせてくれた。人が自分を変えるには本当に苦しい過程があるのではないか。病はそういう苦しみを当然のこととするために用意されるのではなかろうか。私は今日身体が内部から燃えるように痛いと訴える人にめぐり合った。それは治らない病ではなく、治るための第一歩を踏み出したから痛み始めたのではなかろうかと考えた。これは書きながら考えついたことだった。書いてよかった。
あらすじを書いてしまって申し訳ないが、興味のある方は是非とも鑑賞してください。