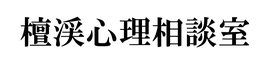カウンセラーとして自信がありますか、私のうつ病は治りますかと問われると、私は自信が無い。自信は無いけれども、きっと治ります、治るように努力しましょうということになる。
治りますと答えると、治らなかったとき、治るといったのに治らなかったではないかと責められても仕方がない。昔々あるカウンセラーは治らなかったと責められたそうだが、おそらくクライエントはカウンセラーに信頼感をもてなかったのだろう。信頼感をもてないカウンセラーにカウンセリングを受けることが間違っている。そのクライエントはあまり治る気が無かったと思われる。だから、治らないのである。治る自信が無いのである。自信が無いというより治る勇気が無いのである。治るのが怖いのではないか。
治ろうという気があるとお互いに全力を尽くして考えるものだ。真剣な話し合いになり、治るか治らないかわからない漫然とした面接にはならないはずである。
臨床心理士の資格を取るに当たって、自信はないけれども、資格を取ったらしっかりと勉強しようという人が多いのではないか。かなり勉強して少し自信ができてきたから資格をもらうというのではない。資格を取ったら、資格に値する自分になろうと考えるのである。そういう人が多いように思う。
ところで勉強して自信ができるかというと、なかなかできない。だから、結局勉強にも身が入らない。
心理面接の経験を積み、いろいろな研究会に出て、人の意見を聞き、自分の意見を述べて、人々と交流しているうちに次第に自分はどれくらいの力量の人間かわかってくるのではなかろうか。心理面接や研究会の経験で培われるものは自信というほどのものではなく、これから可能性の世界へ向って進んで行く勇気みたいなものではなかろうか。未知の世界への跳躍の勇気、大江健三郎の『見る前に跳べ』は極端だが、事前によく調べてなおわからない世界への跳躍の勇気である。
心理面接の世界は一人ひとりみんな違うので、これで良しというところは無い。
私はスーパーバイザーの中でも年長者なので、私に認められるか否かは重大なことらしい。しかし、私に認められることを期待している人がいるようである。それは間違っているのではないか。私がOKと言ってもクライエントや仲間がOKと言ってくれなくてはどうにもならない。クライエントがあなたとともにやっていこうという姿勢になったときカウンセラーは未知の世界へ自信をもって跳躍するのではないか。
生きるということは未知の世界への出立であり、自分のいのちをかけた勇気のいることである。自分が自分自身の主人にならないとできないことである。
遠藤周作は小説『スキャンダル』のなかで、主人公勝呂を通じて「主人持ちの文学」を批判している。キリスト教という主人を戴いた文学、キリスト教的なきれいな文学を書く人もいるが、それはキリスト教という主人を戴いた文学である。問題は小説のなかキリスト教的に解決される。それがキリスト教という主人を持った小説である。遠藤周作はそういう小説は書かなかった。キリスト教徒でありながら人間として日本で生き、小説家であることの苦しみを書いたと主張している。
私たちカウンセラーはフロイトを主人として、あるいはユングや河合先生を主人として心理面接を行っているのではないか。もし、そうだとしたら、私たちはフロイトやユングや河合隼雄を主人としてクライエントに相対していることになる。クライエントはそれで果たして満足してくれるのだろうか。それはフロイト屋や、ユング屋のチェーン店に過ぎないではないか。
教会の牧師やお寺のお坊さんでも真剣に悩みに直面する人のところには悩める人が集まるように、フロイト屋もユング屋もいる中で本当に心の問題に直面するカウンセラーのところにクライエントが行くのではなかろうか。本当に自分の悩みに直面した人にクライエントは会いに行くのではないか。本当の悩みに直面した人は自信といえるものは何もなく、あるのは悩みとともに歩みましょうという姿勢である。
ダンケではそういうカウンセラーを育てて生きたい。