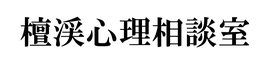先頃、岡本かの子にいて書いた。かの子は夫だけでなく恋人たちからも支えられ、芸術に勤しみ、息子岡本太郎を育てた。そして岡本太郎は大阪万博で太陽の塔を制作した。そのアイデアの奇抜さに人々は驚いたが、あれが母、岡本かの子の像と考えると納得できるのではなかろうか。岡本かの子に生き方は、あの像のように奇抜で偉大だったのではないか。
それに比べると円地文子が小説『女坂』に書いた女性像は何とも悲しく、痛ましい。この小説を現代の女性はまともに読めないのではないかと思った。その生き方は60年前までは当たり前だったかもしれない生き方だった。時代は変わってその古い生き方は私でさえ古いと思う。しかし、私の相談の中でもそれに近い事例があったから、この現代社会の片隅には女坂の世界があるかもしれない。
小説『女坂』では夫が妻に女を探させて家に住まわせ共に暮らした。夫はその女ばかりでなく終には息子の嫁とも関係を持ってしまう。嫁もその関係を楽しむ。果ては長男の孫が小間使いの女を身ごもらせてしまうのでその女の面倒も見る。妻は孫の愛人の世話までして一生を終える。死に臨んで妻は海にざんぶりと投げ込んでくださいと願う。愛人まで家に引き入れて暮らすことは昔も稀だったのではないかと思うが、岡本かの子の家庭と比べるとまったく対称的で、興味深い。岡本かの子は東京中の花屋の薔薇の花を集めて埋葬されたのと比べると、その違いの大きさに驚かされる。
男が家の外に妾を持つことは遠い昔からあった。妾が沢山いた場合その面倒を見たのは女中頭であろう。女坂の場合、妻が女中頭の役目までしなければならないところにこの物語の悲劇がある。夫の経済力がないとこのようなことになるのかも知れない。
『女坂』の主人公の姓は白川で、熊本の出身ということになっている。
白川は熊本市の中心を流れる川で昔は集中豪雨でたびたび氾濫した。私が子どもの頃も毎年橋が流れ、川下の人々は災難に遭った。小説の物語は下々の弱い女性たちが性欲の氾濫に苦労する話である。作家はこのことを意識していたであろうか。単に男尊女卑ということで熊本を選んだのではないか。
愛が性欲の氾濫によっている場合はこの小説の世界のように暗い、何も輝くものの無い世界である。しかし、岡本かの子の場合のように愛が精神的な高まりを呼び起こすとき、それは輝かしい精神的な成果を生むのではなかろうか。岡本かの子と『女坂』を比較したとき、その違いに驚いた。そして女性が強くなった今、岡本かの子が生きた世界が開け始めていると心理臨床の現場で感じている。