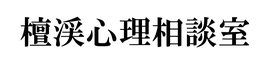『1Q84』は村上春樹さんの河合隼雄先生対する追悼の気持ちを込めた小説だというのが最初の読後の感想であった。
この小説の中には河合隼雄先生に関係することが沢山出てくる。
村上さんは思うところがあって河合隼雄先生に会いに行き、『村上春樹河合先生に会いに行く』という本までまとめられた。自我が強くどんな批評家にも屈しない小説家が心の分析家に会いに行くということはよほどのことがないとできないのではなかろうか。おそらく村上さんはご自身の心の問題の深みに達するために河合先生会いに行かれたのだと思う。そのことはまた別のエッセイに書くことにする。
小説『1Q84』の主人公は青豆と天吾と小学校の同級生である。この二人を一人の人物にまとめると、それは河合隼雄先生なる。先生のペルソナは数学科を出て物語に関心を持つ人であり、アニマ像は強い意志と責任感のある女性である。河合隼雄先生を因数分解的に述べるとそうなる。河合隼雄先生=(天吾)(青豆)(X)。意識の中心としての自我は村上さん自身で、河合隼雄先生のペルソナとアニマを設定し、ユング心理学の考えをしっかり織り込んで出来上がったのが『1Q84』である。ある部分は成功し、ある部分は未完であり、次の小説が楽しみである。
主人公の一人青豆の性格は冷徹で自分の目標に一心に向かっていく。その強固な意志、何事も自分が当面する課題は自分の責任で実行し、人に頼まれ引き受けたことは楽しみとしながらいのちをかけても果たしていく責任性は、専門職としてまとめられている。それは著者村上さんの一面かもしれないが、河合隼雄先生の大切な一面でもあったと思う。
楽しみながら時には命もかけて果たしていくところは村上さんの旅行記『遠い太鼓』や『辺境・近況』によく表われている。それらの小説にあらわれている村上さんの態度、それを集約すると青豆の性格になるのではなかろうか。旅行記は現実であり、青豆は夢の像(アニマ)である。アニマは無意識の態度、無意識の基本的行動パターンを表すものである。
もう一人の主人公天吾は数学科出身で塾の講師をしている小説家、つまり、物語を作る人である。河合隼雄先生も数学科出身で一人一人の物語を発見する仕事を第一とされていた。この河合隼雄先生の似姿を天吾に見ることができる。
河合先生に会いに行って、その交わりから、村上さんは親子ぐらいの深い経験をされたのではなかろうか。その結果として、小説では主人公天吾の父親として河合先生は登場してくる。天吾は子どものとき父親に連れられて歩き回らされるが、実際はいつもそれくらいの気持ちで河合先生に就いて行かれたのではなかろうか。
父親は老齢になって施設に入りほとんど口をきかない人になっている。
ほとんど口を利かないというのも河合先生の一面であった。サービスをしなければならない人に対してはすごくしゃべり冗談もどんどん出てきた。懇親会での態度はそうだった。しかし、サービスの必要がない場面では無口で必要なことだけぽつんと話しされる人であった。突然自分の思いをボソッと言われるのでびっくりし心に残ることが多かった。この『1Q84』の中でも、最初に父親を訪ねて行った時の会話はその特徴をよくあらわしている。
天吾がふと思い立って父親を見舞いに行く。案の定父親は肝心なことはしゃべらない。
「僕は天吾です。あなたの息子です」というと「私に息子はおらない」という。「僕の父親は誰なんですか」と聞くと「ただの空白だ。あんたの母親は空白と交わってあんたを産んだ。私がその空白を埋めた。」
その説明にもわからない天吾に父親は「説明しなくてはそれがわからんというのは、どれだけ説明してもわからんとういうことだ」という。
僕は空白の中から出てきたんですか?と天吾は気づく。
そこで「この男は空っぽの残骸なんかじゃない。ただの空き家でもない。頑強な狭い魂と陰鬱な記憶を抱え、海辺の土地で訥々と生き延びている一人の生身の男なのだ」と天吾は思う。
「説明しなければわからないことは、説明してもわからない」は河合先生の信条であったと思う。グレートマザーという言葉がはやったとき、朝日新聞の天声人語の欄にグレートマザーを説明してほしいと出たとき河合先生はそれには答えられなかったと思う。「説明しなければわからないことは、説明してもわからない」として無視されたのではなかろうか。
「説明しなければわからないことは、説明してもわからない」と同じく天吾に執拗に接近する怪しげな男牛河のことばも天吾の頭の中で自動反復するテープのように繰り返す。
「私が言いたいのはですね、世の中には知らないままでいた方がいいこともあるってことです。たとえばあなたのお母さんのこともそうだ。真相を知ることはあなたを傷つけます。またいったん真相を知れば、それに対する責任を引き受けないわけにはいかなくなる。」
このことばも私の記憶の中に河合先生のことばとして自動反復している。
天吾は父親に次のように述べる。
「僕がずっと求めてきたのは本当のことだったからです。自分が誰で、どこから来たのか、僕が知りたいのはそれだけだった。でも誰もそれを教えてはくれなかった。もしあなたがここで真実を話してくれるなら、僕はもうあなたを憎んだり、嫌ったりはしない。それはぼくにとって歓迎すべきことです。」
真実を知ること、それはユング心理学一つの柱である。フロイトは隠された心理を暴くことが大切だと考えたが、ユングは隠された真実を知ることと考えた。隠されたことを知ることと真実を知ることとは微妙に違う。フロイトの隠された心理は現実の事実である。ユングのそれは実存的な真実である。真実については次のくだりがある。
「僕は何物でもない」・・「たった一人で海に投げ出され、浮かんでいるようなものです。手を伸ばしても誰もいない、声を上げても返事は返ってこない。僕はどこにもつながっていない。曲がりなりにも家族と呼べるのは、あなたのほかにはいない。そしてあなたの記憶は、この海辺の町で一進一退を繰り返しながら、日々確実に失われていく。真実の助けがなければ、僕は何ものでもないし、これから先も何ものにもなりえない。それも実にあなたの言うとおりだ。」
そして「知識は貴重な社会資産です」と父親は棒読みのように言った。この発想は河合隼雄先生の発想に似た村上さんのことばではなかろうか。内向的な私の立場からすれば、知識は貴重な内的資源ですということになる。
この後天吾の真情の告白が続く。
「僕の母親はどんな人だったんですか」・・・「僕は誰かを嫌ったり、憎んだり、恨んだりして生きて行くことに疲れたんです。誰も愛せないで生きていくことにも疲れました。僕には一人の友達もいない。ただの一人もです。そして何よりも、自分自身を愛することすらできない。なぜ自分を愛することができないのか?人は誰かを愛することによって、そして誰かから愛されることによって、その行為を通して自分自身を愛する方法を知るのです」
孤独の問題は村上さんの次の大きなテーマであろう。
村上さんは河合先生の影響を受けて相当にユングの本を読んでこの小説の参考にされたのではないかと思われる。その点はまた機会を改めて述べることにする。
物語のおしまいに父親の主治医から連絡が入る。父親は昏睡状態になったので面会に来てほしいという。天吾は仕方なしに父親を訪ね、昏睡状態の父親に面会する。
河合隼雄先生が病に倒れられて昏睡状態で病床に11カ月もの間ベッドに寝ていられた。その間誰も会っていないと思う。昏睡状態であることはわかっていたが、それ以上のことは誰に聞いてもわからなかった。だから誰も会っていないのだと思う。
先生は天理病院のICUで人口呼吸器をつけてではあるがしっかりと生きていられたらしい。亡くなられた後の新聞の記事や伝え聞くことから総合的に判断すると先生は昏睡状態でるが脳は生きていたのではないか。脳幹をやられ呼吸は困難であったが幸い前頭葉は立派に生きていたと雅雄先生の言葉が新聞に出ていた。先生の知人が亡くなった知らせに、身体がピクリと動いたということも亡くなられてから聞いた。先生は11カ月もの長い間ベッドに寝たきりだったのに褥痩もできず、身体はお世話をする人がびっくりするほど状態が良かったと後で聞くことができた。
医師は天吾に次のように説明する。
「しばらく前から慢性的にあまり良い状態ではありません。・・・お父さまは昏睡状態にあります。・・・どこがとりたてて悪いというわけでもないのです。・・・生命をいじしようとする自然な力が、目に見えて水位を落としているのです。・・・点滴は続け、栄養は補給しています・・・老衰するような年齢ではありません。それに基本的には健康な方です。・・・定期的に行っている体力の測定ではかなり良い結果を出しておられます。問題らしものはひとつとしてみあたりませんでした。・・・なるべく早くお会いになった方がいいと思います。話をすることはできないかもしれませんが、あなたがお見えになれば、お父さんもきっと喜ばれるはずだ。・・・お父さんは、なんというか、とても手のかからない人でした。」
村上さんは何も話が出来なくとも先生に一目会って自分の思いを伝えたかったと思う。その気持ちが上記の医師のことばに出ている。
医師から父親が昏睡状態になったので訪ねてくるようにと言う電話を受けた天吾はふかえりに「猫の町に行ってくる」と言う。
猫と河合隼雄先生は深い関係にある。先生は以前に新潮社から『ねこだましい』という本と出された。この本は新潮社から出ているし、しかも猫の話を集めてそれについて書かれた本だから何か変な本だと思う人もあるようだ。しかし、この本をよく読むと、この本がセルフやアニマ・アニムスに関する本であることがわかる。如何にも専門書でないようで、ユング心理学の中心的概念、セルフに関して、いろいろな猫にまつわる話に関連させながら述べた専門書だと思う。専門書だから岩波から出しても良さそうだが、この本が編集者の主導で出来たので、新潮社になった。一般書の出版社から専門書が出ていることに河合先生のたましいの概念の特殊性を感じる。
河合先生のたましいの概念は独特で、ユングとセルフどこか違っている。河合先生はめったにセルフという言葉を使われなかった。代わりにたましいという言葉を使われた。たましいにはアニマ・アニムスという意味とセルフという意味と二つ入っているのではなかろうか。
また、先生の好きな二律背反の要素もあり、表題の『ねこだましい』が文字通り猫魂とねこ騙しを含んでいると述べられ、裏表紙には村上春樹さんから借りたとわざわざ断って、猫の写真が掲げてあり、その猫の影がいいと書いてある。河合先生のたましいには影があるのである。ユングのセルフに影があるという記述はないと思う。セルフにも影があるというのは河合先生の独自の考えである。先生は自分の独自性をひそやかに示しておられるのが常であった。
つまり、猫の町に行くことはセルフやアニマの世界、つまりたましいの世界に行くことを意味しているのである。天吾が猫の町に行くことは、たましいに出会うことを予示している。
天吾は父親に会いに行く。医師は言う。
「たとえ深い昏睡状態にあっても、人によってはまわりの話し声が聞こえる場合もありますし、その内容をある程度理解できる場合もあります」
たぶん村上さんも病床の河合先生には会っておられないだろうと思う。しかし、村上さんはきっと昏睡状態の河合先生に話しかけたかっただろうと思う。
天吾は昏睡状態の父親に話しかける。話しても通じているかどうかは全くわからない。でも看護婦さんは「話しかけるのはいいことです。大丈夫、きっとお父さんには聞こえています。」と言う。
天吾は聞こえているかいないか全くわからないなかで、孤独に昏睡状態の父親に向かって自分の半生を語った。それは空しい作業に感じられた。
「その男はとても穏やかな顔をしていた。・・・深い昏睡状態に入り込んだまま、彼の前でひっそりと死んで行こうとしていた。自分が本当の父親でないことを天吾に事実上打ち明け、それでようやく肩の荷を下ろすことができて、どことなくほっとしているようにも見えた。我々はそれぞれの肩の荷を下ろせたわけだ。ぎりぎりのところで。」
この面会は小説の中のことであるが、互いに肩の荷を下ろすことができたと述べられている。特に村上さんはこの『1Q84』を書いてギリギリのところで、河合先生のところで解決しようとした問題に答えをだすことができて肩の荷が下りたのではなかろうか。
おそらく誰もが昏睡状態の河合隼雄先生に会うことができなかったので、一人一人が村上さんのような内的な作業をしなければならないと思う。
父親は処置のためにベッドを離れ、部屋には誰もいなくなった。天吾は孤独になった。天吾もその場を離れた。しばらくして部屋に戻ってみると、空のベッドの中に空気さなぎができていた。予想もしないできことだ。孤独な語りかけは無意味ではなかった。昏睡状態の父親を前にして自分の半生を語ったことによってそこに魂が生まれてきたのである。河合隼雄先生の分析ではクライエントが先生の涅槃像を夢で見ている。先生は面接中死んだように眠っておられることもあった。それを考えると特にこのところの記述には夢と現実が混交していることがわかる。これは空気紡ぎの結果である。
空気さなぎにはすでには割れ目ができていて天吾はその中に青豆を見出して温かい手の命のぬくもりを感じた。しっかりと握りしめた手のぬくもり、それはこの『1Q84』の重要なキーポイントの一つである。村上さんはここで河合先生の手のぬくもり、あるいは、心のぬくもりを感じ、反復されたのではないかと思った。
このように解釈したところに私自身の気持ちも込められていることがわかる。これは私個人の心の投影で村上さんとは違うかもしれないが、・・
村上さんは、河合隼雄先生との出会いで、10歳のときのいのちの経験を回想し、その経験を青豆のようなたましいとの出会いとして小説にまとめられたのではなかろうか。何故か今まで心の奥深くしまいこまれていたいのちの経験が、人を愛することのできるようになった男の物語としてこの小説に描かれた。『ノルウエイの森』の愛のレベルから魂の愛のレベルへの進化が起こっていると思う。
このようなたましいのいのちの回復が昏睡状態の河合隼雄先生への語りを通して行われ、追悼小説ともいえるこの『1Q84』に間に合ったことは不思議である。シンクロニシティとも言えると思う。なぜなら『海辺のカフカ』の死の世界から『1Q84』の夢幻ともいえる世界の想像の作業、物語の創作には相当なエネルギーの集中があったのではないかと想像する。生身の河合隼雄先生でなく、昏睡状態の河合隼雄先生を想定しての物語り、現実にはこの世に存在しない河合隼雄先生との対話を通じての内面への探求があったに違いない。内的な深い作業の結果この小説が出来上がったとも言えるのではなかろうか。現実に多くの人が村上さんを同じような作業を一人一人しているに違いない。