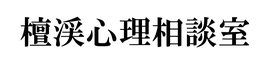河合隼雄先生は「たましいの復権」というエッセイで、性の抑圧がなくなった現在最も抑圧されているものはたましいではないかと書いておられる。
現代はお笑いが流行っている。河合先生もよく冗談を言って人を笑わせておられた。
お笑いは人々をホッとさせ、我を忘れる時を与えてくれる。みんなで笑うとほっこりするのだが、笑いの世界に入って一人になっているのではないだろうか。笑いで人とつながろうとするとしょっちゅう笑いのタネを考えておかねばならない。お笑い芸人はいつもいつも寸暇も惜しまず考えている。ある落語家が一日のスケジュールを円グラフで書いてテレビ番組で見せていた。その記憶によると、15分刻みでゆっくりしている時間がない。お笑いの萩本欽一さんもお風呂に浸かると気持がだらけるのでシャワーしか浴びないと語っていたことがある。お笑いのいのちを生きる人は焼けたフライパンの上の水玉のようにいつも弾けているのではなかろうか。そういう状態の心ではたましいはどのようになっているのであろうか。
冗談を言って人を笑わせたときの河合隼雄先生はしばしばすごい形相になって別なことに集中しておられた。その場の人々は河合先生の冗談を聞いて笑っているのに、先生はまったく違う深刻な世界に目が向いているので、それを見た人はぎょっとしてその姿が忘れられず、人に言わずにはいられないらしい。このような様子を何人もの人が書いている。
河合先生の冗談は自分への視線を回避するためのもので、ご自身は自分のいのちにかかわることに思いを巡らせておられたのだろうと思う。
先生が書かれるものはいのちにかかわるものだったと思う。いのち、それはたましいのことである。
愛や憎しみといった感情レベルの心ではなく、愛や憎しみを越えたところにたましいというこころがある。心はコロコロ変わるからこころというのだという説がある。確かに愛は憎しみに変わり、憎しみは愛に変わる。大事なのは愛や憎しみの背後にあるいのちである。いのちは目に見えないし、これと言って掴みどころもない。河合先生はたましいをつかむには物語しかないと考え、後に中世の物語文学の研究に力を注がれた。
たましいを掴む方法は物語だけではない。和歌も俳句も、歌謡も舞踏も、人々は沢山の表現方法を用いてきた。しかし、それでも余程修行しないとものにならない。
それらは今世の中に満ち溢れている。テレビに展覧会や出版物の中にあふれるほどあって、あふれるものの中に私たちはたましいを見失っている。
生き物が死ぬとたましいがなくなったと感じられる。たましいが離れて出て行ったら物になっている。たましいが抜けると身体は抜け殻になる。
生き物から抜け出たたましいはどうなっているのか。たましいに個別性などあるのか。たましいは生き物の中にいる間はそのものの名前で生きていてあるとわかるが、抜け出てしまうと名前のついたものの消滅とともに行方知れずになってしまう。万葉の昔には山にたなびく雲の中にたましいを見ていた。それは火葬の煙が雲になったものだ。たなびく雲のようなものだから普遍的にいつでもどこであると言って良いのではないか。
河合先生はユング派の分析家ヒルマンの言葉making
soulを引用して、たましいを自分の中に養ってそれをあの世に持っていくと書いておられる。そのたましいも煙と化すならたましいもあの世へはもって行けないのではないかと私は考えている。ただ、河合先生の業績や思い出を心に留めている私たちは先生のたましいを受け継いで生きていくことはできる。たましいは先輩後輩の関係や家の伝統として生きている。椿は椿らしく牡丹は牡丹らしく生きている。その中には椿の、あるいは、牡丹のたましいが生きている。そう考えるとたましいは生物学的なものであると考えた方がよいのではないかと思う。
河合先生に初めて会う前に西から太陽が登る夢を見たロサンゼルスのユング派の分析家シュピーゲルマン先生が、河合先生のお墓参りをされたとき、晴れた空に輝く太陽に丸い虹がかかった。それを見たシュピーゲルマン先生は河合が天国から挨拶に来たと感動されたという。その日輪は墓参に同行された樋口和彦先生が写真に取られ、その写真は滝口俊子さんの『夢との対話』に紹介されている。河合のたましいが天国から挨拶に来たというのは不思議なことであるが、その経験はシュピーゲルマン先生の心の中の経験であって、私たちは驚きをもって聞くだけである。シュピーゲルマン先生はそれだけたましいを感じ取れる人だったと思う。
たましいこそは分別のない、名前が付けられない、個別性の無い、しかもいのちのある存在である。たましいはこの世界には充満していて、いのちがある。それは井筒俊彦の意識の形而上学で述べられた真如の世界ではないか。意識、つまり個別性を認識する能力で世界に充満しているたましいを感じ取る力を養うことはできるのではなかろうか。
牡丹が牡丹らしくあるために、自分が自分らしくあるために、このいのちを含んだたましいの世界に触れる必要がある。私たちは夢や箱庭を通じてそのようないのちにかかわる仕事をしているのではないかと思う。