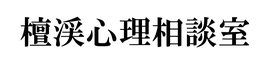長谷川泰子
6/23は檀渓心理相談室の室長であった西村洲衞男先生の一周忌でした。この1年間いろいろなことがあり時間の流れ方がよく分からないような感じでした。しかしこうして1年過ごしてみると、1年というのはひとつの節目になる時だと実感します。なんとかここまで来たということでほんの少しほっとした思いもあるのです。
モーニングワークという言葉があります。喪の作業と訳されています。実際に喪失体験をした人たちとの話し合い、臨床的な経験・知見から導きだされたものだと思います。様々な理由から大事な人を亡くしたのにも関わらず深く悲しむ機会を得られず、悲嘆にくれるのが当然だという時にしっかりと悲しむことができなかった場合、不安定な精神的状態が長く続くことがあります。
悲しんでいる人を見ているのはつらく、見ている方も苦しくなります。そのために周りががんばれ、気持ちを切り替えろと励まし、悲しみからの早い回復を期待してしまったりもするのですが、それはしっかりと悲しむ機会を奪うことにつながります。回復のためにはまずは何よりも素直にしっかりと時間をかけて悲しむことが必要で、だからこそ“モーニングワーク”の重要性が強調されたりもしたのでしょう。
わざわざモーニングワークなどと言わなくとも、昔から“喪中”という一種の社会的な制度があります。喪中だからと年賀状のやり取りを控えたりお祝い事の席を避けたりしますが、社会的場面・人間関係から距離をおき、様々な制約や義務から離れて悲しみにひたる時間を作り出す制度だと言えます。悲しみの渦中にある人を周囲の刺激から守り、一定の時間を与える機能を持ったものだとも言えるでしょう。
モーニングワーク、と言われると妙な違和感があるのは私だけでしょうか。ワークという言葉がどうも引っかかるのです。モーニング、喪失を体験すること、深く悲しむことは、取り掛かるべき仕事でも終えるべき作業でもありません。実際は、自分の自然な気持ちに従い、その時その時感じる喪失を味わい、それをくぐり抜けた先で、あれがモーニングワーク、喪の作業であったと、もしかしたらそう名付けることができるかもしれない、そんな体験なのではないかと思うのです。
こういうことを考えたのは、最近、ある人から教えられた言葉によります。フランスの思想家、ロラン・バルトの「喪の日記」という本の中に「それぞれの人が自分なりの悲しみのリズムをもっている」という言葉があると教えられ、早速この本を取り寄せてみました。この本はロラン・バルトが母を亡くした時のメモをもとにまとめられたもので、この言葉も彼の実体験から出てきたものです。
それぞれがじぶんなりのリズム、ペースを持っています。そのリズムは最大限尊重した方がいいのではないでしょうか。本人が本来のリズムで生き、悲しみを体験していれば、いつかは自然にこころが動き出していくのではないかとも考えます。そういった誰もが本来持っているこころの自律的な動きを信頼してもいいのではないかとも思います。
これは喪失体験に限ったことでもないかもしれません。こころの自律的な動きを信頼するカウンセリングでありたい、そんなふうに考えた西村先生の一周忌でした。