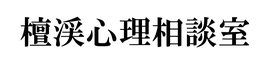西村先生のパソコンに保存されいた文章です。最終更新日時は2007年5月、文章の形式から学会誌に投稿するものとして用意されたものと思われますが、発表はされておらず、未発表原稿としてこちらに掲載します。この文章にも法華経従地涌出品十五(正しい教えの白蓮 十四さとりを求める者の大地の裂け目よりの出現)が引用されています。
なお英文アブストラクトにある所属は当時のものです。
転移・逆転移を超えて
西村洲衞男
1 はじめに
心理臨床において転移・逆転移という考え方は大変重要であると考えられている。フロイトやユングが無意識や心理療法の理論を組み立て、その中で転移・逆転移は立場を越えて理解される重要な概念になっている。フロイトやユングの遺産で生きている現在のわれわれは心理臨床の経験に基づきこの概念についても吟味し検討する必要があると思う。最近刊行された氏原・成田によってまとめられた『転移・逆転移』( 氏原・成田 1997)はそのよう仕事の一つで、大胆な試みであったと思う。しかし、この仕事もフロイトが提出した転移・逆転移という概念を理解し体験的に極めているかを視点としていて、転移・逆転移を越えた視点までは開かれていない。
われわれはこれまで多くの臨床経験を積み、さらに多くの治療者が発表した数々の事例に接してきた。そこで見たものはフロイトやユングが作った概念を超えているように思われる。われわれは転移・逆転移の真理を理解していないように思われ、いつまでも不全感を抱いているが、実は転移・逆転移という概念では説明しきれないような現象を多く経験しているように思われる。そこで転移・逆転移に係わる問題を省み、我々の心理学の言葉で説明する試みを提案したいのである。
2 心理療法の実際において転移・逆転移として捉えられている現象は心理療法の重要な問題である。最近、氏原・成田の二人は現在の長い臨床経験を積んだ、中堅の指導的な立場にある心理療法家に『転移・逆転移』について自己の経験に基づいて論文を書かせ、両者の編著として『転移・逆転移』を刊行した。この本は転移の問題について多面的に深く掘り下げようとした試みとして高く評価されると思う。著者たちは自己の経験に基づいて逆転移についても率直に論じているので、読者も自然とこころ開かれる好著である。
筆者は転移についてはユング派の立場で考えて来たので、ユングの『転移の心理学』やマイヤー,C.A.(Meier 1989) の論文よって考えてきた。従って、転移については教育分析を受けながら、自分とクライエントの係わりについて深く省察することが大切だと考えてきた。ユングは転移は投影によって成り立っており、投影は無意識だから起こっているのだと考えていた。転移は無意識に基づいており、しかも、転移-逆転移は互いにフックのようになり、クライエントの掛けるものと治療者の掛けられるものとが組になっていて、それらは無意識の心的内容であるから、意識化は難しく、生き通す以外に抜け道はないと考えてきた。そして、多くの人が転移-逆転移の問題に関して大変厄介な問題であるとする現象は治療関係に起こる恋愛問題か境界例のクライエントとの間におけるぎくしゃくした心的距離の定まらない問題であると考えてきた。従って、これらのことが『転移・逆転移』においてどのようにあつかわれているかが大変興味があった。
著者の一人、岡田は治療関係に起こる若い女性との恋愛問題に関しては、ある治療者が明らかに不適切な対応をしたために起こったクライエントの自殺未遂の後をフォローした事例を簡潔に述べ、この問題は厄介な問題であるに違いないが、それは治療者が節度を守ることによって乗り切ることができると考えている。
さらに、岡田は自己の経験から治療関係をクライエントのたましいが演ずるドラマの舞台であると考えている。クライエントはたましいのドラマを演ずる役者であり、治療者は観客であり、時には演出家であり、劇場の支配人であると言う。この考えた方は今までにないユニークな考え方である。転移は治療関係の中に展開されるクライエントのドラマであり、その展開が治療過程となり、ドラマの終わりは終結を意味するのである。
岡田が紹介している中年女性の事例は父親との関係がドラマとして演じられたドラマの適切な事例である。クライエントは治療関係の中で父親との関係を再現し生きることによって転移を解消したのであった。転移された関係を生き抜くことはこうして成されると言う好事例である。
Lowenfeld,M.は「世界技法」(今日の箱庭療法)を転移を必要としない技法として発表しているが、箱庭療法こそは内的なドラマの表現であり、コラージュ法も同様に理解されと考える。岡田の転移はドラマでるという考えは興味深い発言である。
治療関係における恋愛問題は若い女性のクライエントに多い筈である。『転移・逆転移』に取り上げられている事例の年齢を見ると、20代の女性のクライエントを男性、それも若い男性の治療者が受け持っている場合がほとんどで、次に40代の女性のクライエントとやはり男性の治療者が問題になっている。興味深いことに30代の女性はほとんど問題になっていない。女性は発達的に20代と40代においてロマンチックになることがこの事実から推測される。
前掲書に参加している女性の治療者は二人である。二人とも転移-逆転移の問題はほとんど関係がないらしく、若い女性のクライエントに手こずって苦労する若い男性治療者を横目に見て笑っている菅の文章には、さもありなんとこちらも笑ってしまった。李の論文は事例のない観念的な論述に終始しているので、激しい恋愛性の転移-逆転移に振り回された経験がないのだろうと思われた。
また、男性の治療者の一人、藤原は治療技法の関係から転移を治療には無関係なこととして無視していく態度を取っており、転移-逆転移はほとんど問題になっていない。
転移-逆転移は心理療法の基本的であり、αでありωであると編著者の一人成田は言っている。同様のことをユングも言い、ユングのその言葉にフロイトも深く感銘し、二人の信頼関係をつなぐ絆の一つになったと思われる。この背景には、両者とも女性のクライエントの恋愛性の転移の処理に苦労し、その反省があったからだと推測される。その苦労は彼らの心理療法の仕事に熱心に係わってくる女性のクライエントであっただけに、心理療法全体を暗雲で覆うほどのものであったろうし、転移-逆転移こそが心理療法の全体に通じる根本問題であると考えたとしてもおかしくない。そしてわれわれもまた同じ轍を踏み、両巨頭の考えをそのまま受け継いで今日に至っているのではなかろうか。
現在も転移-逆転移を心理療法における祈りの決まり文句の如く唱えてきた背景には、心理療法の理論家の多くが男性の治療者であったことも深く関係していると思われる。彼らは若い女性のクライエントに苦労した経験が少なからずあって、フロイトやユングと同じ轍を踏んでいたことが指摘されよう。実際、『転移・逆転移』の著者たちのほとんどがそうなのである。これからもずっと同じことが繰り返され絶えることはないであろう。
3 転移-逆転移の所謂「厄介な問題」は、恋愛性の転移であり、それは心理療法の中の特殊な問題にすぎない。これにとらわれていると転移・逆転移に係わる多くの問題を見落としてしまうのではなかろうか。われわれは治療関係の中で起こる現象をもっとつぶさに観察し、われわれの目で見たものをわれわれの心理学で説明していくことが大切ではないかと考える。そこでわれわれの理論的なリーダーの考えを見てみよう。
転移には激しい転移と深い転移があると河合は指摘した。(河合 1990)この考え方はフロイト派とユング派の違いを考える上で重要なものである。
激しい転移は恋愛性の転移や批判的・攻撃的な転移を含むもので、フロイト派の転移に相当するだろう。それに対して深い転移はユング派の無意識の同一性やMeier の言うコンプレックスの共有を意味している。グレート・マザー・コンステレーションはその典型であろう。現在、グレート・マザーという言葉は流行らなくなって久しいので、わからない人も多いに違いない。グレート・マザーという言葉が流行ったころ、グレート・マザーのコンステレーション(布置)が論じられたが、それは一種の転移である。母親と子がグレート・マザーとその子どもとして布置されている関係である。母-子ども関係における保護的で干渉的な母親をグレート・マザーと見做し、母親が子どもの自立を抑制している場合に適応された。
しかし、理論的に見ると、グレート・マザー・コンステレーションは本来コンプレックスの共有現象を指しているのであって、そこに係わっている人がグレート・マザーに影響されやすい状態になっていることを意味する。従って、子どもだけでなく母親もその影響を受けており、母親もグレート・マザーの子どもとして自立性に乏しく、自己主張をせずに流れに身を任せていく生き方しか出来ない状態を意味していたのである。
このように考えていくと、影の共有とかアニマ・アニムスの重なりということを考えなければならない。それらの現象は観念的にはわかるとしても、心理療法の実際において治療関係に現れる現象を教育分析なしに理解することは困難であったと思われる。
人格の影の部分は劣等機能であり、未発達の性格である。それらは無意識の領域にあるので外界に投影され、転移的な関係として対人関係に彩りを添える。影を投影した相手に反発したり、嫌悪したりして対人関係が妨害される。分析においてこの事実を意識化しても何とかなるほどのものではない。統制可能なものにするにはその未熟な機能を発達させねばならない。それには長い年月を要したり、本来の性格とは反対の性格特徴を伸ばさなければならないために却って内向的な人が外向的になろうとして神経症的になったりする。そこで影の人格に反発したり、否定したりして戦うことを止め、自分の中に劣等な性格の部分のあることを認め、つまり、影を引き戻して自分の中にその存在を認め、自分よりもすぐれた人と妥協したり協力したりして行くことを学ぶことが現実的である。
アニマ・アニムスの部分は異性の性格の要素を代表するとされている。全ては無意識的な性格であるから、外界に投影され、主に異性関係を彩る要素となっている。この部分は人の関心を最も引くところで、比較的に分かりやすい。
内的には、アニマ・アニムスは無意識の代表として、意識する自我に相対している。それはほとんど衝動的な部分であり、エロスや攻撃などを伴う無意識の衝動や態度となって行動に現れている。夢の中ではしばしば異性として表象され、その異性の性格は無意識の衝動や態度や生き方を反映している。
現実の行動面では、その人の無意識の行動パターンや、見知らぬ他者、特に世間に対する態度や対人関係における雰囲気として現れているので、人はアニマ・アニムスに余り気づくことがない。社会に目が向いているとき人はアニマ・アニムスとは反対のペルソナを堅持することに気を遣っていて、意識の背後に潜む無意識の態度には気付きにくい。われわれは自分の醸し出している雰囲気を知ることは難しい。これを知るには、他者の態度の微妙な変化を注意深く観察し、自分の中に起こっている緊張がどのようなものであるかを知り、外界と内界の呼応性を慎重に考慮することが必要である。さもなくば、夢に現れたアニマ・アニムス像が内部に持つ性格と夢主の行動様式を比較検討することである。このような作業は影の認識と比べると大変難しいので、ユングは影の分析は弟子の仕事であるが、アニマ・アニムスの分析は師匠の仕事であると言っている。
アニマ・アニムスの分析と言っても、出来ることは自我の発達に応じたことしかできない。それ以上を望ならばアニマ・アニムスのもつエネルギーを生かしていくための自我機能とペルソナを強めなければならないであろう。
ユング派の心理療法家が見ている転移は以上のような影やアニマ・アニムスや老賢者やグレート・マザーなどの元型的なコンプレックスによって動かされている深層の関係なので、意識化して無力化することはできず、コンプレックスによって引き起こされる危険を回避しながら、生き抜くことによって次のステップに上がっていくしかないと考えてよいのではなかろうか。
さらに、元型的な布置だけでなく、治療者とクライエントが同じコンプレックスを持ていて、その克服が問題になることがある。例えば、治療者もクライエントも共に攻撃性を強く抑圧していて現実適応のために攻撃的・積極的な生き方を考えていかねばならないとき、両者は共に苦しまねばならない。この状況においては、攻撃性を発展させるか、より深く傷つき苦しみながら攻撃的でない生き方を見出した者が治療者となるのである。互いに出口が見出せないときは、酷く困惑した関係になるか、膠着した関係に陥ったりする。この際、より一層強く生きる力を必要とするので、治療者は責任ある者として分析を受け、自ら問題を克服することが必要である。
4 心理療法の理論は心の現象を観察するための観測機器であると成田はある講演で語った。「転移-逆転移」と言う観測機によって治療関係の感情的な部分をかなり詳しく観察することができることは間違いない。
転移の考え方には基本的に幼児期の親子関係が再現反復されたものという考えがあるので、治療関係の現象の中から幼児期の親子関係によって形作られた関係の持ち方だけを見出そうとし、それ以外の治療関係の現象を見ない可能性も生じてくる。
また、治療者に対して専ら愛情欲求を向けて来る場合、幼児期において愛情が不足していたであろうと想像する。しかし、愛情欲求が満たされない関係であったからこそ今求めているのであり、過去に得られなかった関係を求めているのであり、過去の親子関係の転移とは言い難いのではなかろうか。つまり、われわれが転移と呼んでいるものの中には過去の関係の逆もあり得ることを考えなければならない。感情的な関係を全て転移と呼ぶことは概念を曖昧にすることであり、その曖昧さの故にわれわれの理論的な防衛が歪んだものになってしまうのである。
転移について、更に若干考えてみよう。一つは転移という見方そのものが治療者の転移となり得ること、第二は転移の原因探究という幼児期の親子関係の詮索の作業が果たしてクライエントにとって役にたつものかどうか検討する必要があることである。第三は転移が無いように見える関係についてである。
a 理論的な見方という逆転移
治療関係において転移があるという見方がそもそも逆転移である可能性がある。精神分析的に言えば、投影性同一視ということになるであろう。例えば、治療者に理解し受入れて欲しいと執拗に訴えてくるクライエントの依存性は、クライエントが親との関係において理解して貰おうとして受け入れて貰えなかったことの反復であると言う見方を治療者がすると、クライエントに過去の親との関係を改めて見直させ、親からの独立を成し遂げて行くことが必要なことであると考えるであろう。こうして依存欲求を自分の問題に戻されるとクライエントは治療者に甘えられなくて怒り、攻撃するであろう。この攻撃も母親に対する感情の転移であると返されるとクライエントは欲求不満状態に陥り苦しむことになるであろう。精神分析ではこのような経験をしているクライエントがままある。クライエントは単純に治療者に自分の今の思いを分かって受け入れて欲しいのかもしれないのである。自分の心の理解者として存在してほしいのに、見たくないものを見せられることになる。それを幼児期の親子関係の分析の出発点とされると、クライエントは求めてもいないことをさせられ、終わることのない不安に苛まされることになる。精神分析の理論的な立場からはクライエントの依存的な態度の背景の心理分析として正しいかもしれないが、その治療方針は治療過程ではこういうことがあるはずだと言う学習した心理学的な見方をクライエントの押しつけることになり、理論的な見方の逆転移となるのである。
精神分析に限らず心理療法においては学習した心理療法の理論的な見方が逆転移される可能性がある。心理療法の技法や理論的な枠組みを意識する立場ほど、治療者は心理学的専門家の意識が強くなり、理論の投影に嵌まって、治療関係の現実が見えなくなる危険性がある。
事例研究における心理学的な理解はかなり理論的な関心に沿ってなされるので特に理論の投影に満ちている。スーパーヴィジョンが時としてほとんど役に経たないのはこのようなことも原因していると思われる。スーパーバイザーが理論的な立場から放った意見はスーパーバイジーの内的な経験を素通りしてしまうことがある。事例研究会においてはスーパーバイザーが特に分かりやすく理論的に説明しようとすると、理論の当てはめになり、事例の現実が見えなくなってしまう危険性がある。スーパーバイザーの中には自分の心理療法の理論の構築に熱心な人もあり、一方その取り巻きには理論的な支えを望む人も多いので、事例や治療者の心理という現実から遊離していく可能性も大なのではないかと思う。あるスーパーバイザーのコメントを聞いたとき、事例報告の細かい内容から溢れるほどいろいろな説明が出てくるが、それはスーパーバイザーの治療経験を彷彿とさせるものではあっても、事例の治療過程とはややずれていて、事例を提供した治療者やクライエントは置き去りにされていると感じたことがある。このスーパーバイザーは自分の心理療法の考え方を話すのが好きであって、われわれが期待するスーパーヴィジョンをする気はほとんどなかったかもしれないので、この批判は的外れであるかもしれないが、心理学理論の投影になるようなコメントの延長線上にこの例があると思うので敢えて取り上げ、反省の素材とした。優れたスーパーバイザーと呼ばれる理論家も、その人に学ぶ者も共に投影性同一視に振り回されるというのがわれわれ心理療法の世界に生きる者の宿命であろうか。
b 過去の親子関係の見直し
治療関係に現れた依存的な態度や攻撃的な態度を取り上げ、それを手掛かりとして過去の親子関係を見直すことは心理療法の重要な作業である。
クライエントが親から心理的に独立するためには親を見直すことが必要である。その作業の手掛かりとして転移の解釈がある。そして転移を通してこそ親子関係の深層の分析が可能であるという仮説をわれわれは持っているように思われる。
先に述べた事例のようにクライエントから強い愛情欲求の転移が生じている場合、治療者を厳しかった母親との同一化しているとして、その転移として取り上げていくことが心理療法の重要な要点であると考える立場がある。この作業はクライエントの愛情欲求をそのまま受け入れることなく、過去を振り返って親子関係を見直させることになるので、クライエントは欲求不満になって、時としてクライエントに苦痛な作業をしいることになる。それは本当に必要なのかと疑いたくなる事例に遭遇すると、われわれは改めて過去の親子関係の見直しをどの様な形で進めていくか、多くの事例に基づいて検討してみる必要があると思う。
c 転移を通した見直しが難しい場合
親子関係を省みるとそこには深い悲しみと人には話せない恥ずかしいことばかりが出てくることがある。両親が離婚し捨て子同然であったにしても、目覚めた意識をもち大人や周囲のものごとを観察し判断してきた人は、不幸な状況にあっても自分の目で観察し判断するという主体的自我領域を持つに至り、経験してきたことを基に世界について語ることができる。苦しい惨めな経験であってもそれは自分の責任ではなく、この世界を作ったものの責任である。だから、生きてきた世界について客観的に語ることができるのである。例え不幸な環境に育っても、自分の子どもだったころのことを話せる人は幸せである。
このように自我が目覚めているときは親子関係の検討が可能である。自分が未だ目覚めていないときに大人の判断に振り回されながら、状況を漠然と見てきた場合には、子ども時代の経験を問われたとき漠然とした記憶しかない。取り立てて言うべきものはない。子ども時代のことはほとんど思い出せないという人もある。こういう人にあなたが子どもだったころはと問うのは人間的に恥ずかしい部分の覆いを剥ぐような感じがする。
恵まれた家庭で過干渉的な親に育てられた、いわゆる良い子は人よりも早く大人らしさを身につける。アダルト・チルドレンは子どもらしさを失って大人になった人の典型例である。子ども時代に親の考えや期待を敏感に観察して生きて来た人は親の常識や道徳的に期待される価値に縛られ、自分の感情や意欲を見失っている。心の生活のガイドラインとしては親の考えや期待の観察しかない。自分の経験はと問われたとき何も応えることができない。親の期待に依って生きてきた人には主体的な経験がなく、自分で観察して考えた内容もない。自分が自分の経験に立っていないのである。
われわれ心理学者は理論的な先入観として、人はみな目覚めて自分で判断しているという前提で考えていないだろうか。良い子やアダルト・チルドレンが内的な世界に目覚めていないという現実はわれわれの先入観を破った。
酒乱の父親が家庭で怒り狂うのはいつも親の期待に添えない生活をしている自分たち子どもの責任であるというクライエントの認識や、子どもの家庭内暴力は転移を越えた視野を要求しているように思われる。
両親の不和や嫁-姑の諍いがあってその影響が家庭のなかで最もおとなしい子どもに向いていることがある。その子は母親やお婆さんの気持ちをよく理解したがために、一家の問題を背負い犠牲者となる。その子どもの内面には家庭内の争いが渦巻いていて悲しみを感じる余地さえもなく、自分の心の領域を見たときそこにはただ空虚な心の世界が広がっている。一群の不登校の子どもの世界にそれに近いものが感じとられる。
この空虚な心から転移は何も生じないし、親子関係の回想は困難を究めるだろう。
自分以外の価値基準に沿って生きた人が、その価値基準は無意味で何も役に経たないと知ったとき、同時に自分の価値基準は何もないことに気づく。自分は一人で、孤立していて、世界の何処にいるのかさえはっきり定位できないだろう。閉じこもることによって自分を定位しなくては不安で仕方がない状態にある。そこには脱け殻のような自分と、感情的なつながりのない形だけの人間関係が広がっている。そういう感情が生きられていないところでは転移関係は空虚であるから何も見えない。そこには何もないから人間関係を一からつくる作業が待っている。人間関係を作る機能がほとんど失われた状態から、基本的な信頼関係を作る作業をしなければならない。閉じこもりの事例が難しい訳はそこにある。
5 新しい観点の必要性
最近、事例研究会で以前の考え方とは合わないものにしばしば出会うようになった。その一つはやせ症や不登校などの事例に多く見られる親子関係の疎遠さや親の係わりの少なさである。
ある母親は過食嘔吐に悩む娘に対して、「早く直しなさい、いつまで病気しているの、早く病気を直して結婚しなさい」と言った。われわれは普通病気の娘を持つ母親に対して優しい暖かいい思いやりのある愛情溢れる看護的な態度を期待する。けれども、何年も娘の過食嘔吐に付き合ってきた母親は反抗的にしか係わって来ない娘にもはや優しく接することができない。互いに思いのたけの不満をぶっつけ合って対決せざるを得ないくらいに緊張をはらんだ関係になっている。このような関係で過去を詮索すると怒りと当惑を増幅するだけで、建設的な関係が何も得られないことがある。
また、最近は子どもが不登校や摂食障害になったとき、子どもだけをクリニックに行かせて自分係わりたくないという親も出てきた。小学生の子どもが親から面接料をもらってそれを治療者に渡して面接が始まるという事例にも出会うようになった。このような事例では親面接はときたましか出来ず、子どもはほとんど治療者との関係に支えられて自立して行かねばならなくなっている。風邪をひいたら医者へ行き、薬を貰って飲んで良くなるように、不登校になったらカウンセラーのところに行って治して貰うという考え方になってきたのである。子どもはもう既に自分で考えて生きることができる程に成長したのだから、後は自分で考えて生きて生きなさいと言われているようである。
15年以上も兄の家庭内暴力に悩まされてきた青年は、兄の入院によって静かな生活を見いだしたが、心の中は空虚で、これからどのように生きて行ったらよいか皆目見当がつかない。そのために長い間世間とは没交渉で過ごしている青年がある。
このような事例を今多くの臨床心理士が抱えていると思われる。これらの事例について転移・逆転移は心理療法のαでありωであるとして単純にその見方を当てはめていくとかなり問題の事例が出てくるのではないかと思われる。そこで事例の問題の性質に適合したアプローチを考えて貰いたいと思うのである。
摂食障害についての適切なアプローチが現在見いだされているかどうか筆者は不明である。しかし、面接料を握りしめて独りでやって来る子どもには保護者的なサポートを当てねばならないし、引きこもって対人関係を恐れている青年には基本的な信頼関係を築くことが求められるであろう。これらはクライエントの当面する問題に対する常識的な対処である。これが転移の扱いや箱庭療法や描画療法などの技法の適用よりはるかに大切なことである。われわれは心理療法の理論に捕らわれるとき、しばしばこの常識の大切さを専門家意識の故に忘れがちになるのではなかろうか。これが専門家意識の逆転移の危険性の一つである。
6 刺激と反応としての治療関係
心理面接において、何でも自由にこだわりなく話し合える関係が理想であり、その関係の中で、クライエントの全ての話の内容は治療者との関係を言い表しているものとして考えるという見方がある。例えば、この間叔母さんにあって少し恥ずかしい思いをし緊張したとクライエントが述べたとき、治療者に対して恥ずかしく緊張したのかもしれないと考えるのである。このような見方をスーパーバイザーに徹底されると、クライエントの深層心理がありありとわかると感じるが、ある人はそんなことを一々考えていたら堪らないと感じるだろう。人様々である。だから心理療法では治療者とクライエントに合ったアプローチが必要であることがわかる。しかし、現実には治療者の技法とクライエントの心理のミスマッチがかなりの問題を引き起こしているのではないかと考える。
愛着欲求を満足したい子どもが多くいて、欲求不満をもっている子どもの親にしばしば子どもにベタベタされることが嫌いな親が少なくないことは多くの臨床家が経験的に知っていることである。それに対して心理療法家にも同様にスキンシップの苦手な人達がいることは案外考慮されていないのではなかろうか。学校では生徒にまつわりつかれ易い先生がある一方、ほとんど求められない先生もある。心理療法家も当然そういう性格があって、子どもの愛情欲求を満足させやすい人とさせにくい人がある。子どもは本能的に甘えさせてくれそうな人を雰囲気や直観で知り関係を深めたり離れたりしていくのである。このことを考えに入れて転移を考えて行く必要があるのである。
精神分析では転移を受ける治療者は中立的で、クライエントの見えないところにいれば自分を隠せると考えている。けれども、初対面のとき、治療者の存在全体から現れる雰囲気は隠しようがない。この知覚はほとんど無意識レベルで行われているので捉えにくい。愛着行動を喚起するような性格の人がいると愛着欲求を満足したい人が強い係わりを求めていくし、もし反対に、愛着行動が不得手であると、そこでは愛着行動が起こりにくいと考えられる。治療者が愛着欲求を抑圧し、クライエントもまた同じである場合は、治療関係は膠着状態になって中々進展しないことになるであろう。
従来は転移はクライエントの側から幼いころの親子関係が治療者に対して投げかけられると考えられて来た。治療関係を外側から見ると正にその通りであるが、反対に内側から見ると治療者の持つ人格的な資質がクライエントの転移を引き起こしているとも考えられる。治療者の持つ転移の解発刺激がクライエントの愛着行動を開発しているのである。
ローレンツ(1970)の比較行動学の考えに依って、治療関係を行動の解発刺激とそれに対する反応として見ていくことは転移-逆転移という見方よりも遥かに一般性があって、転移以外の治療関係の要因も考察の対象に入れることができ、治療過程におこる様々なトラブルばかりでなく治療的な要因も明らかにする可能性を開くのではなかろうか。
転移-逆転移の関係で多くの男性治療者が困っている恋愛性の転移においては、先ずクライエントの恋愛衝動と男性治療者の魅力が、女性から見たら無防備に、相互に刺激しあって起こっているのである。恋愛感情の中には女性のアニムス-女性の中の男性的性格-が働いており、やさしい理解ある対応が求められることになる。多分、そこでは母親との関係では満たされなかった温かい母性的な、求めに対して素直に応ずるような受動的な愛が希求されている。恋愛感情の中に父親の愛と母性的な愛の希求が混交している。
恋愛感情の中に見られる愛情欲求は親子関係の転移というよりも、恋愛感情の発現に際して個人の内部から開発された、過去においては開発されず、今始めて解発された愛情欲求も込められている。過去の親子関係が不満足なものであったので、クライエントは満足を求めているのである。クライエントは自分の見いだした新しい対象に対して満足を求めて行動する。治療者の異性的な魅力と優しさが解発刺激になって、クライエントは可能性に向かって新しい行動を起こし、同時にこれまでの愛情不足を補おうとしているのである。それは転移ではなく、新しい生き方の解発なのである。
7 治療関係の基礎である共感的関係
ユング派には”Wounded Healer" 「傷ついた治療者」という概念がある。自らも傷つき悩みを深めた者が治療者となるという考え方である。神話学者ケレーニイはギリシャ神話における医神が傷ついた神であることを指摘した。ユングはこの点に注目したのである。同じ考え方は仏教の法華経( 坂本・岩本1959) の中にもある。
法華経従地涌出品十五(正しい教えの白蓮 十四さとりを求める者の大地の裂け目よりの出現)には次のように説かれている。偉大な志を持ってさとりを求める者たちが、教えを説き広めたいので教えを請うと、仏は私の教えを広める者は大地の中から湧いてくると答える。すると大地に裂け目ができ、そこから数知れぬ菩薩たちが湧き出てきて、仏はその菩薩たちに説教をしたというのである。仏教の教えを広める者は偉大な志を持った者ではなく、暗い大地の底から湧き出てきた、つまり人間的な世界で苦悩を生き抜いてきた菩薩たちだと言うのである。
心理療法において教育分析が必要な訳は、分析を通して精神分析やユング心理学を学のではなく、自分の内面を深く見つめ、深層に動いているこころに意識のフォーカスを当てているということであろう。
この自分の深層のこころの動きにフォーカスしていることが傷つくことであり病むことなのである。われわれは健康で悩みがないときは体のことも心のことも意識しない。病気をし心傷つき悩むとき、深く自分を省みる機会をつかむ。治療者が深く傷ついていると、深く悩み自分の深層を深く省みるはずである。日々の自分を省みる作業が治療者を作って行くのである。この作業を一人で行うか、それとも自分よりもより心の視野の広い人(分析家)と共に行うかによって、その成果が異なるだろう。一人で自分を省みる人は独りで悟る人であり、内面の探究を助けるであろう。一方、分析家と共に自分を探究する人は人と共に自分を省みることができるようになるであろう。教育分析によって培われた資質は治療関係の中で相談する力として働き、クライエントの相談意欲を解発するのである。
治療者の内省力や相談する人格的な資質がクライエントの相談意欲を解発するように、クライエントの強い相談意欲が治療者の内的な相談能力を解発する可能性もある。クライエントに深くかかわり、困難な治療過程を生き抜くことによって治療者になることができたという思いをもっている人は少なくない。
このレベルの関係は目に見えず、こうだという証拠は何もないが、われわれの周囲で起こっていることを静かに見ると見えてくる現象である。物書きの指導者の下から物書きの旨い人が育ち、説教癖のある人から説教の上手い人が育ち、立ち回りの上手い人の下には上手く立ち回る人が出てくる。このような様々な資質をもった大きな人格の人からは様々な人物が育って来るのである。このような関係を見ると、人格の深層の資質が人を育てて行くことが明らかになる。教育分析が大切な訳は心理学を学ぶためのものではなく、真に自分の分析を深めることにある。教育分析が個人分析と呼ばれる訳もそこにあるのである。
8 治療的な態度と治療関係
ユング派の心理療法では、カルフの言う母子一体性、つまり安全で温かく保護された関係の中でクライエントは自由に自分を表現し治っていくと考えている。精神分析では自由で率直な対等な話し合いの中でクライエントは内的な感情を自分で理解し表現し統制し自立していくことが出来るようになると考えていると思われる。ユング派の態度は受容的であり、精神分析の人の態度は対決的である。このように単純に割り切って考えることは著者の独断であるが、便宜的に治療的な態度を受容と対決に分けて考えてみる。
受容的な態度で接すると混乱するクライエントがある。それはヒステリー親和型の性格のクライエントの場合、温かく受け入れられていると、クライエントは自分の全てを受け入れて貰えると幻想する一方で、何も手応えがないので自分が何処にいるのか、自分の本当の感情が何なのかさえわからなくなってくる。そして受け止められない不安は底知れぬ不安となって治療者への執拗な係わり、依存となって現れる。この混乱状態は乖離現象であり、所謂境界例の問題である。クライエントの不安と攻撃にさらされ窮地に陥ったとき、治療者が腹を括って自分の治療方針や治療構造についてはっきりと述べると、相手は意外におとなしくなって安定するのである。境界例のクライエントに手こずった経験のある治療者はこのような経験をしている筈である。境界例が一時期流行っていたのに最近余り流行らなくなった。これには様々な要因が働いていると考えられるが、その一因は治療者の治療的態度が受容的なものから対決的に変化したことにあると思われる。ヒステリー親和型の性格のクライエントに対して受容的治療態度を取っていると、症状は一時消えるかもしれないが、結局は次第に悪化し、依存性が増大し、治療者の積極的な支えなしには不安が増大するばかりになる。大抵は治療者が耐えられなくなり、何処かで治療者が怒りを爆発させるか、治療構造を厳しくすることによって困難を回避するのではなかろうか。
あるタイプのクライエントは治療者の受容的な態度に向けて退行し、赤ん坊になる。この退行状態が治療者や親にとって受容可能なときは人生を最初からやり直すことになり、劇的な効果が得られることがある。青年期のクライエントが親に抱いてもらって風呂に入ったり、哺乳瓶でお乳を飲むような経験を幻想や遊びで経験することによって立ち直る機会を持つことはあり得ることである。しかし、その退行を治療者が受きれないと、クライエントは退行したまま混乱状態が続くことになる。これは治療者が引き起こした問題である。
治療者が対決姿勢で望む場合、自分の弱さ惨めさを理解し受入れてもらおうとうするクライエントは常に治療者の突き放しに拒まれ、益々惨めになり弱くなる。クライエントは傷つき抑うつ的になって、人生への希望を失う。元々治療者に対して一言自分の意見を言うことが出来ない人達は、努力して良く学んだ権威のある精神分析の理論を背景として自信に満ちている治療者に全く頭が上がらない。かといって治療関係を解消するわけにもいかない。治療はまだ終わっていない。と言うよりもまだ問題が出たばかりだ。問題点を明らかにされるばかりで少しも前に進まない。何時もスタート地点に立っているようなものだ。治療者から離れるのはさらに苦しい。この解決されない問題を誰に救って貰えるのか、呆然としている。そういうクライエントに相談された人も少なくないと思われる。
自分の弱さ惨めさを理解し受け入れて貰いたい人は受容的な治療者のところに行くべきであるし、自分の弱みを見せず只管頑張って自己顕示的に生きている人は対決的治療者のところに行くべきなのである。そうすれば境界例も自信喪失によって強い抑うつ状態になったクライエントも救われるのではなかろうか。
治療関係をこのように性格の適合性で見ていくことは治療関係の混乱を避けるために是非とも必要なことだと考える。
9 まとめ
転移・逆転移から見える世界は様々で広い。それを超えた世界はさらに広い。ここでは筆者の経験や見聞したことがらを基に思いつくものを述べた。少しずつではあるが、これから従来の理論から抜け出してわれわれの、そしてクライエントにも役に立つ心理療法の理論が発展させて行きたい。
本論で述べたかったことをここにまとめておく。
① 転移-逆転移の問題は厄介な問題であると考えられているが、実は厄介なのは、男性治療者と女性クライエントの間に起こる恋愛性の転移である。それ以外の転移は余り問題とならない。
② 治療者が学習した理論的な見方が逆転移として治療関係を歪めていることがある。
③ 治療関係は治療者とクライエントの資質がかかわり合う刺激と反応の関係であると考えた方が適切である。
④ その1例として、治療者の態度とクライエントの性格が不適合の場合、クライエントに重大な混乱が発生する可能性があることが上げられる。
ヒステリー性性格のクライエントに対して治療者が受容的な態度で積極的に係わると、クライエントの心理は乖離的となり、離人感や強い不安が生じ、いわゆる境界例となる。これは治療者が対決的は態度をとってクライエントと一定の距離を置くことによって治まる。
一方、自分の弱さや惨めさを受け入れて貰いたくて依存的になるクライエントに対して、対決姿勢で、いわゆる分析的な態度で依存欲求の親子関係の転移の分析を行うと、クライエントは依存欲求を受け入れて貰えなくて、欲求不満となり、攻撃的になったり、反対に悲観的抑うつ的になったりする。
以上のようなことから、われわれは転移というあいまいな概念を離れて、治療関係の中に起こっている感情的な関係を刺激と反応という観点から詳しく観察し、適切な対応を研究して行くことが望ましいと考える。
文献
氏原 寛,成田善弘編著 転移-逆転移 創元社 1997
河合隼雄編著 臨床的知の探究 上 創元社 1990
マイヤー, C.A 秋山さと子 訳 ソウル・アンド・ボディ 法蔵館 1989
坂本幸雄 岩本 裕 法華経 岩波文庫 1959
ローレンツ,K 日高敏隆 久保和彦訳 攻撃 みすず書房 1970
Abstract
LOOKING BEYOND TRANSFERENCE/COUNTER-TRANSFERECE
SUEO NISHIMURA AICHI UNIVERSITY OF EDUCATION
This paper will examine the problem of transference/counter-transferece
issue and explains that it is the romantic transference between a male therapistand a young or middle age female client. This paper also explains that the
moter figure transference, in which the client seeks affection is not only
transference from childhood experiences, but also a desire to obtain love from
an understanding, kind male figure. Moreover as the issue of counter-
transference, it is possible for a therapist to put his/her psychological
theory onto client's psychological state, and it tends to disappoint a client.
Therefor, I sggested to look beyond transference/counter-transference
and to revisit the therapeutic relationship from the view-point of stimulus-
response. From this view-point, borderline issues is considered to be
a response of a client historionic personality to a positively accepting
attitude of a therapist. Similary the severe depression is considered to be
a response of a client with self-punitive character and who lacks self-esteem
to a confrontative psychoanalysis.
key word: transference-counter-transference, romantic transference,
stimulus-responce.