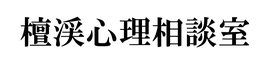長谷川泰子
学生時代に「フォーカシング」の実習があった。フォーカシングとは、こころ・身体の奥に感じられている言葉にならないような微妙な感覚(フォーカシングでは“フェルトセンス”という)に注意を向け、それに触れることによって気づきを得ようとするもので、来談者中心療法を確立したロジャースと一緒に仕事をしたジェンドリンによって提唱されたものだ。学部生時代の実習で、大学院生の人とペアを組んで5回フォーカシングを体験し、レポートを書いた。
自分の内側にある微妙な感覚に注意を向け、それがどんな感じかを味わうといっても、はじめは何をどうしたらいいのか分からない。具体的な指示や教示のようなものもほとんどなかったように思う。どちらの方向に注意を向けたらいいのかよく分からないし、いろいろ思ったり考えたりすることはあっても、それが「フェルトセンス」にあたるものなのかもよく分からない。これでいいのかなぁ、よく分からないなぁと思いながらやっていたのをよく覚えている。
学生時代はフォーカシングに強い関心を持つこともなく実習での体験だけで過ぎてしまったのだが、今になってあの実習をやっておいて良かったと思う。フォーカシングは心理臨床家の訓練にも役立つと言われているが、実際、自分がカウンセリングにおいて相手の話を聞いている時は、フェルトセンスという言葉で表わされているような自分自身のこころ・身体の奥にある微妙な感覚に注意を向け、そこから得られたものを大事にしていることが多い。頭で考えた知的な理解や感覚的な判断などももちろん頼りにするが、話を聞きながら自分が奥の奥でどういう感じを抱いているのか、深いところでどういうものが湧いて来るのか、難しい時こそ、その微妙な感じを頼りにして進んでいくところがある。
フォーカシングは自分のなかにある小さくかすかな声を正しく聞き取るためのひとつの方法だと言えるだろう。深いところでささやかれる小さな声は、「~すべきだ」「~したい」というようなはっきりした分かりやすい考えや強い思いを主張する大きな声にかき消されやすいが、見えにくい本質をキャッチしていることが多い。本質的なものは時に表面に現れているものとは異なり、だからこそ大きな声とは対立・矛盾するように思われて、わざわざ聞く必要がないと軽視されたり無視されたりすることがある。しかし本当のことは何かが大事になるカウンセリングの場では、クライエントの小さな声に耳を傾けていくことが大事で、そのためにはカウンセラーの側も自分自身の小さな声に耳を傾け、かすかな感じを逃さず、しかもそういった微妙なもののなかから頼れるものを選び取っていくことが必要になる。地図もない光も差さないジャングルから抜け出ようとする時には、ちょっとした感じ、ささいな感覚にも細心の注意を払わないといけない。
村上春樹の小説「ねじまき鳥クロニクル」のなかで、ある登場人物が「良いニュースというのは、多くの場合小さな声で語られる」と語るところがある。小さな声でささやかれることは、はじめ意味のないものに聞こえたり、大きな声と矛盾したりするようなものに思えても、最終的に“良いニュース”につながっていくのではなか。大声の主張に惑わされず、かすかな声を聞き取っていくのがカウンセリングであるようにも思う。