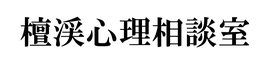長谷川泰子
先日、たまたまあるセミナーに参加していた時に、フロイトが自分自身で論文にも書いている、ある体験について聞いた。フロイトが寝台車の個室(コンパトーメント)にひとりでいた時に、列車が激しく揺れてとなりのトイレに通じるドアが開いた。そこにガウンを着た見知らぬ初老の男性が入ってきた。相手は帰る場所を間違えて入り込んできたのだろう、間違えてますよと声をかけようとしたところでその男性はトイレのガラスに映った自分自身だと分かった、という体験だ。
この話を聞いて、河合隼雄先生も同じような体験をどこかで書いていたなと思い出した。河合先生の自伝で語られている、ユング研究所で資格を取るためスイスに留学していた時のエピソードだ。「イタリアの連中とワーワーやっていて、あるときダンスに行ったんです。ぱっと入って行って、フッと見ると、一人異様なやつが向こうからくる。アッと思ったら、ぼくが鏡に映っているんですよ」(「河合隼雄自伝 未来への記憶」新潮社)。
自分自身の生の姿をリアルタイムで外から見ることはできない。せいぜい撮影した映像を後から見るだけだ。録音された声を聞くと、とても自分自身の声とは思えずに戸惑うことがあるが、映像についても同じような戸惑いが生じる。最近はスマホのせいでというか、おかげでというのか、とにかく写真を撮る・撮られる機会が多い。昔に比べて写真に写った自分自身の姿にある程度の慣れは持ちやすくなっていると思うが、それでもやはり写真の自分を見ると軽い幻滅を抱く。写真の加工技術がどんどん進化するのも、自分を加工したい、写真に写った自分自身の姿を何とか受け入れられるようにしたいという思いを誰もが持つからではないだろうか。
遠藤周作の小説に「スキャンダル」(新潮社)という作品がある。もうひとりの自分、認めたくない自分自身の影におびえる男の話だ。河合隼雄先生がこの小説を絶賛されていて、文庫の方には河合先生の解説も収められている。フロイトは自分自身の体験を糧にして精神分析の理論を作ったが、自分を冷静に見て、それを理論にまでまとめ上げるほどの客観性と自我の強さがあったから、寝台車のなかでもうひとりの自分を見ることができたのではないだろうか。河合先生もスイスに行ったからこそ、ユング研究所での体験があったからこそ、もうひとりの自分自身に正面から出会うことができたのかもしれない。
自分自身を客観的に見ることは難しい。それを受け入れることはもっと難しい。しかし、どんなに嫌だと思っても、もうひとりの自分はいつも自分のとなりにいて、引き剥がすことも消し去ることもできない。いくら見ないふりをしていても、いるということは変わりない。もうひとりの自分におびえてそこから逃げ続けるよりも、なんとか向き合って話し合って妥協点を見出し、協力を目指したほうがこころの自由度は増す気もするのだが。