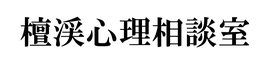源氏物語が好きで、これまでにいろいろな人の訳で源氏物語を読んできたが、結局いつも読み返すのは初期に読んだ与謝野晶子の訳である。
源氏物語を読む人が光源氏に文句を言いたくなるエピソードが「若菜上」にある。ざっとあらすじを書くと、若菜の帖では光源氏は40歳前後、いよいよ地位も安泰となってきているが、ここへ来てはるかに年下の女三宮を妻として迎えることになる。それまで正妻のような立場だった紫の上よりも女三宮の方が身分が上であることから、光源氏が妻として迎え入れることになれば、女三宮の方が正妻になる。娘の将来の心配した女三宮の父から頼まれ、表向きはしぶしぶ、しかし女三宮(おんなさんのみや)が光源氏にとって永遠の憧れの女性、藤壺の中宮と血縁関係にあったことから、彼女に似ているのではないかと内心大いに期待しての承諾だった。紫の上は自分と光源氏が暮らす六条院に新たに立場が上の女性が入り込んでくることに深く悩むが、それでも表向きは明るく振舞い、女三宮とも仲良くやろうと女三宮のいるところに出かけて行ったりもする。しかしよりによって光源氏はそういった時に、昔の恋人の朧月夜(おぼろづきよ)に会いに行く。
朧月夜は源氏のかつての政敵の妹に当たる人物で、ゆくゆくは天皇のもとに入内することが決まっていたのに源氏が横取りして密かに会っていた女性である。それが発覚したために源氏は失脚し、京から逃れて須磨で謹慎せざるを得なくなった。紫の上が辛い気持ちを抑えて、なんとか上手くやろうと努力していた時に源氏が会いに行ったのはトラブルの原因となったこの女性なのだ。
源氏物語を読んでここの場面にぶつかると「光源氏というのはなんというひどい男だ!」と憤慨する人も多いようだ。しかし私は、与謝野訳で読んだ時には何の引っ掛かりも持たず、源氏の行動がひどいとも思わないまま読み過ごしてしまった。ところが次に谷崎潤一郎の訳を読んだ時には、この場面にぶつかって猛烈に腹が立った。自分の勝手な振る舞いで光源氏は須磨に行き、その間、紫の上も先がどうなるか分からないまま不安な思いで京に残された、しかも光源氏は、謹慎先の須磨でやっぱり女性と出会って子まで設けて帰って来くる。更にまた新たに女性を迎え入れることになり、それでも何とか上手くやろうと紫の上ががんばっているところに、ちょうどいいタイミングだとかつての恋人のところに遊びに行ってしまう。光源氏というのはなんてひどいやつなんだ!と、物語であって実在の人物でもないのに、まるでそういう人間を本当に目にしたかのように腹を立て、怒りが1日中収まらないぐらいだった。
しかし冷静になってみると、与謝野訳ではこの場面に対して特に気にも留めずにスルーしたのが不思議になる。もともとは同じテキストをもとに現代語訳されているのだから、訳者が異なっても内容に大きな変化があるわけではないのだ。専門家に言わせれば、訳者によって大きな違いがあるのかもしれないが、文体や表現が異なるだけで同じ場面に対する反応がこれほどまで変わるとは考えられないだろう。
ただ、後に与謝野晶子は光源氏のことが好きで谷崎潤一郎は光源氏のことが嫌いだった、と書かれているのをどこかで読み、自分自身の反応の違いについて納得できる説明を見つけたような気がした。
訳者の個人的な好悪の感情は、決して直接的に表現はされない。訳者は創作をするわけではない。読みやすくするための工夫はそれぞれにあるだろうが、オリジナルの文章以上のことを付け加えたりストーリーに手を加えることはない。しかしそれでも、やはり登場人物に対する個人的な感情や思い入れなどは、意識していないところでなんとなくにじみ出てくるものなのではないだろうか。ふたりの訳者の光源氏に対する思いの違いが、この場面に対する反応の違いを生んだのだと思った。
プラスの感情にしてもマイナスの感情にしても、はっきりと表に現れなくても、人の思いは深いところで伝わっていくものなのだろう。そんなことを体験した出来事だ。